心臓は収縮と拡張を繰り返すことで、ポンプのように血液を血管に送り出します。
その際、血液が血管の内側に与える圧力を「血圧」と呼びます。
血圧は「収縮期血圧(上の血圧)」と「拡張期血圧(下の血圧)」の2つの数値で表されます。
血管の太さや壁の硬さと心臓が1回の収縮で送り出す血液の量によって血圧値が決まります。
SLEEP APNEA
心臓は収縮と拡張を繰り返すことで、ポンプのように血液を血管に送り出します。
その際、血液が血管の内側に与える圧力を「血圧」と呼びます。
血圧は「収縮期血圧(上の血圧)」と「拡張期血圧(下の血圧)」の2つの数値で表されます。
血管の太さや壁の硬さと心臓が1回の収縮で送り出す血液の量によって血圧値が決まります。

「収縮期血圧」と呼ばれる上の血圧は、心臓が収縮して血液を全身に送り出す時の血圧です。
心臓が最も収縮した時の圧力であり、血管壁にかかる圧力が最も強くなります。
「拡張期血圧」と呼ばれる下の血圧は、心臓が拡張して血液が再び心臓に戻る時の圧力です。
この時、心臓から血管への血液の送り出しはなく、血管壁にかかる圧力は最も弱くなります。

血圧は、自律神経の働きや動脈硬化の状態によって変動します。
リラックスしている時や暖かい時は血圧が低く、活動している時や寒い時、ストレスがある時は血圧が高くなりやすいです。
また、動脈硬化が進行すると動脈壁が硬くなり弾力性がなくなり血圧の変動が大きくなり、血圧サージ(急激な血圧の上昇)が起こることがあります。
このため、血圧の安定には自律神経のバランスを保つこと、動脈硬化を予防する事が根本的に血圧を安定させるために重要です。
高血圧の診断には、診察室血圧(病院での血圧)と家庭血圧の両方が用いられます。
家庭血圧が135/85mmHg以上、診察室血圧が140/90mmHg以上で高血圧とされ、血圧は日々変動するため、家庭での定期的な測定が推奨されます。
| 分類 | 診察室血圧 | 家庭血圧 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |
| 正常血圧 | <120 | <80 | <115 | <75 |
| 正常高値血圧 | 120-129 | <80 | 115-124 | <75 |
| 高値血圧 | 130-139 | 80-89 | 125-134 | 75-84 |
| I度高血圧 | 140-159 | 90-99 | 135-144 | 85-89 |
| II度高血圧 | 160-179 | 100-109 | 145-159 | 90-99 |
| III度高血圧 | ≧180 | ≧110 | ≧160 | ≧100 |
| (孤立性)収縮期高血圧 | ≧140 | <90 | ≧135 | <85 |
※日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」
下の血圧が高い状態は、末梢血管が硬くなっているために起こります。
末梢血管が動脈硬化によって弾力性を失うと、血液が流れにくくなり、血管にかかる圧力が高くなります。
この状態は高血圧と同様に動脈硬化のリスクを高めるため、注意が必要です。
加齢に伴い、血管の弾力性が低下して血流が悪くなり、血圧が上がりやすくなります。
また、自律神経の働きが低下することによっても血圧の変動が大きくなります。
これにより、高齢者は血圧が高くなりやすいと言えます。
高血圧の治療は、心血管病を予防するために重要です。
若年者から前期高齢者の目標血圧は診察室血圧140/90未満、家庭血圧135/85未満です。
後期高齢者や糖尿病患者の場合、さらに低い目標が設定されます。
これにより、心血管病のリスクを減らすことが目的です。
治療による目標血圧値(成人血圧、単位はmmHg)は以下の通りです。
| 診察室血圧 | 家庭血圧 |
|---|---|
| 140 かつ 90未満 | 135 かつ 85未満 |
| 診察室血圧 | 家庭血圧 |
|---|---|
| 150 かつ 90未満 | 140 かつ 85未満 |
| (様子を見ながら下げられれば) 140 かつ 90未満 | 135 かつ 85未満 |
| 診察室血圧 | 家庭血圧 |
|---|---|
| 130 かつ 80未満 | 125 かつ 75未満 |
血圧が低いと心臓や血管への負担が少ないですが、低血圧が続くと全身に十分な血液が供給されず、十分な酸素や栄養が行き渡らなくなります。
その結果、立ちくらみやめまい、疲労感、食欲不振などの症状が出現することがあります。血圧が低いと心臓や血管への負担が少ないですが、低血圧が続くと全身に十分な血液が供給されず、十分な酸素や栄養が行き渡らなくなります。
その結果、立ちくらみやめまい、疲労感、食欲不振などの症状が出現することがあります。

食事の塩分量を意識し、加工食品も合わせて、塩分は1日6g未満に抑えましょう。
アルコール類の過剰摂取は血圧を上げる原因となります。
日本酒なら1日1合、ビールなら中瓶1本を目安にしましょう。
肥満が影響し高血圧に至ってしまいます。高血圧治療を行う上でも先に肥満を解消する事からスタートします。
適切な体重を維持する事は生活習慣病を治療する上で非常に重要です。
喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を促進させてしまいます。
その為喫煙者には禁煙を指導する事は重要です。
受動喫煙にも注意が必要です。
日々の生活でストレスを溜めないようにし、リラックスできる環境を整えましょう。
趣味や十分な睡眠を取ることで心身のリフレッシュを図ります。
通勤時に歩くことやテレビを観ながらのストレッチなど、運動を日常生活に取り入れましょう。
無理のない範囲で毎日60分程度の運動を目指します。
治療中の方は医師の指示を受けて運動を行ってください。
※PDF形式のファイルをご利用になるためには、Acrobat Readerが必要です。
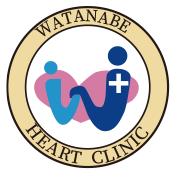


【休診日】日曜・祝日

© 2026 医療法人社団わたなべクリニック